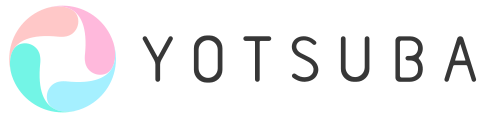産休中の社会保険料はいつから免除?適用される期間・申請手続きの方法を解説!
産休中の社会保険料はいつから免除になるのかや、適用期間・申請手続きを解説します。産休中は社会保険料免除や住民税が免除されるためぜひ申請しておきましょう。また、社会保険料免除のほかに住民税・雇用保険料・扶養控除や、年末調整についてもご紹介します。
産休中の社会保険料免除期間は、先ほどご紹介したように「産前42日間」と「産後56日間」です。双子などの多胎妊娠の場合には「産前98日」となりますので注意しましょう。また、産前と産後を合わせると計98日(多胎妊娠は計154日)ありますが、この期間のうち仕事を休んでいた間のみが社会保険料免除期間となります。
つまり、産前や産後の休暇を取らずにギリギリまで仕事をしていた場合や、出産後にすぐに職場復帰した場合は、社会保険料免除の対象外となりますので、注意しましょう。手続きというと面倒に感じるかもしれませんが、産休を取得するのであれば申請しておいた方がいいでしょう。
(出産手当金については以下の記事も参考にしてみてください)
産休中の社会保険料免除でどのくらいの節約になる?

産休中の社会保険料免除はどのくらい家庭の節約につながるのでしょうか?「社会保険料免除の手続きや申請は大変そう…」「免除といってもそんなに変わる?」と、手続きの大変さと免除される金額を天秤にかけて悩んでいる人も多いでしょう。
妊娠してからはどんどん体重が増えていき、普段の日常生活が大変に感じることが多いですよね。その上「社会保険料免除の申請や手続きなんて…」と思う人も多いでしょう。しかし、社会保険料免除の申請は月額で計算すると、かなりお得になることが多いので申請して損はないはずです。
こちらでは、産休中の社会保険料免除の申請をすることによってどのくらいの節約になるのかご紹介します。また、ギリギリになってから申請するのではなく、あらかじめ書類を書いておくなど前もって準備することをおすすめします。
収入が多いほど支払う社会保険料は高くなる!
まず、社会保険料免除の申請でどのくらい節約できるかを知る前に、日本の年金制度について知っておきましょう。基本的には、累進課税という課税法を適用しており、年収が高い人はたくさん保険料を納め、年収の低い人は少しでいいという制度になっています。
年収別で計算しても、年収が高くなればなるほど多くの保険料を払わなくてはいけないことになります。そのため、年収が高い人ほど社会保険料免除の申請を提出した方がお得ということになりますね。もちろん、年収がそれほど高くない人でも免除された分は払わなくていいので節約につながります。
産休中の住民税の支払いは?免除される?

産休中の社会保険料は免除されますが、住民税の支払いはどうなのでしょうか。こちらでは、産休中の住民税の支払いについて詳しくご紹介します。
産休中でも住民税は免除されない
残念ながら、産休中や育休中でも住民税の支払いは免除されることはありません。中には自分が住民税を払っているかわからない、支払った記憶がない…という人もいるでしょう。会社に所属している人は、特別徴収といい会社の給与から天引きされているはずですので、気になる人は給与明細を確認してみてくださいね。
産休中は自分で住民税を払いに行く必要がある
産休中は会社からの給料が出ないため、給与から住民税の天引きがされません。そのため、自分で住民税を納めにいかなくてはなりませんので注意が必要です。会社の給与から天引きされている状態を「特別徴収」と言いますが、自分で払いに行く場合は「普通徴収」と言います。
普通徴収の場合は、支払う月が決まっています。6月、8月、10月、1月の年に4回です。この時期になると、納付書が届きますので、それを持って自分で支払いにいかなくてはなりません。また、納付期限が設けられており期限を超えると、わずかではありますが延滞金が発生しますので、期限には気を付けるようにしましょう。
産休中は住民税の自動引き落としがおすすめ
妊娠中は住民税の支払いに行くのは大変なことですよね。そういう時は、住民税の支払いを自動引き落としに切り替えるのがおすすめですよ。市区町村の窓口で申請すれば、1,2か月ほどで口座から自動で支払いがされるようになります。産休や育休後に会社に復帰した場合は、特別徴収に自動切換えになるため特に自動引き通し終了の申請は不要です。
産休中の住民税を軽減したいならふるさと納税
また、産休中に限らずに住民税を節約したい場合は「ふるさと納税」も考えてみてくださいね。近年、ふるさと納税という言葉を聞くようになった人も多いのではないでしょうか。ふるさと納税は、任意の自治体に寄付をすることを意味します。その土地や地域に住んでいなくても、応援したい自治体を選んで寄付することができるのです。
選んだ自治体へ寄付をすると、寄付をした金額から2000円引いた金額が住民税・所得税から控除されるという仕組みです。さらに、自治体からのお礼としてその自治体の名産品などが送られてきます。住民税や所得税の控除も受けられるうえに、名産品まで貰うことができるので賢い節税法ともいえますね。
産休中の雇用保険料は発生する?

Recommended
おすすめ記事
授乳中のママへ贈る、カフェインレスコーヒー&ティーおすすめガイド
【確定申告・いつまでに?やるべきか?】わかりやすく順序だてて解説します!!
【夢占い】妊娠する夢の意味とは?何かの警告なのか?その対策とは?
【夢占い】妊娠する夢の意味と心理:状況、感情、登場人物から徹底解剖
妊娠中の性行為はNG?気になる疑問を徹底解説!
妊娠中に心と体を満たすプレゼント5選:本当に喜ばれるギフト選び
さまざまなサインがわかる!!妊娠中のおりものの目安について
【妊娠中のお腹の張りの不安について】原因と対策ーリラックスグッズ3選
【ほっこり】石原さとみ、日本アカデミー賞で“美しすぎるママ”姿を披露
【祝】辻希美さん5人目を妊娠!ママとしての強さと優しさに注目