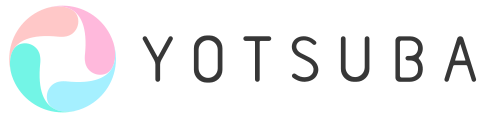産休の期間・給付金の計算方法は?産前・産後休業はいつから?手続きについても!
働く妊婦さんにとって大事な産休ですが、いつから取得できるか知っていますか?今回は、産休の期間や、計算ツール、取得できる条件などをくわしく解説します。更に、気になる産休中の給料・社会保険料・給付金の計算方法や手続きについても取り上げます。
産休は出産予定日の6週間前から取得できると紹介しましたが、出産予定日より前に帝王切開することが決まっていることもありますよね。その場合は、産休の期間はどうなるのでしょうか?
労働基準法で決められていることは、妊婦さんには自然分娩予定日(出産予定日)の6週間前から産前休業を取る権利があるということのみです。そのため、あくまで法律上では、帝王切開の手術日ではなく本来の出産予定日を基準にして産休の期間を計算することになります。
しかし、会社によっては手術日を基準にすることができる場合もあります。この場合は手術日の6週間前から休暇を取れるということになりますね。事前に帝王切開による出産が決まっている場合は、会社の就業規則を確認したり、会社に相談したりしてみましょう。
産休中の給料や社会保険料、給付金は?手続きについても!

産休中の給料や、出産に伴って支給される給付金などの制度とその手続きについても気になりますよね。それぞれ確認してみましょう。
(妊娠に伴い退職する場合は以下の記事も参考にしてみてください)
産休中の給料はどうなる?
産休は休職として扱われます。そのため、基本的には産休中は無給です。給料が貰えない代わりとして、後述する手当て金や給付金が支給されることになります。
会社によっては給料が支給される場合もあるので、会社に確認しておくと良いでしょう。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産したときの分娩費用を補助する目的で、健康保険組合から支給されます。受け取れるのは健康保険の被保険者であるママだけでなく、夫の被扶養者となっているママも対象です。支給額は、赤ちゃん1人につき42万円です(※2)。双子以上の場合はその人数分だけ支給されます。
手続き方法は、直接支払制度を利用するかどうかで変わります。直接支払制度とは、健康保険組合から出産した病院に出産育児一時金を直接支払ってもらうことのできる制度です。病院が直接支払制度に対応していれば、病院で申し込みをすることで手続きを完了することができます。(※2)
直接支払制度を利用しない場合や、直接支払制度を利用して分娩費用が42万円未満だった場合は、健康保険組合への書類提出が必要です。多くの場合は会社経由で行えるので、担当部署に確認しておきましょう。
出産手当金
出産手当金とは、出産の際に収入が減ってしまうママを支援する目的で、健康保険組合から支給されるものです。支給の適応期間は産休の期間中で、産休の日数分の支給額が受け取れます。また、出産日が出産予定日から遅れた場合はその日数分も支給されます。支給額の詳細は後述の「産休の給付金の計算方法は?」を参照してみてくださいね。
受け取るには、ママ本人が健康保険に加入していること、妊娠4ヶ月以降での出産であること、出産のために休業していて無給であるか出産手当金未満の給料しかもらっていないことの、3つの条件を満たしている必要があります。
出産手当金は健康保険組合に申請をしないと受け取ることができません。出産育児一時金と同様、多くの場合は会社経由で申請できるので、担当部署への確認を忘れずに行いましょう。申請書にはママ本人以外にも会社や病院が記入する部分があるので、あらかじめ書類を用意しておくのがおすすめです。
(退職している場合の出産手当金については以下の記事も参考にしてみてください)
産前産後休業保険料免除制度
産前産後休業保険料免除制度とは、文字通り、産休の期間中の社会保険料の支払いが免除される制度です。この制度に申し込むことで、産休中に社会保険料分の金銭負担をなくしながらも、普通に支払った場合と同じサービスを受けることができます。(※3)お得な制度ですね。
産前産後休業保険料免除制度は、産休に入ったからといって自動的に適用されるものではなく、申請の手続きをする必要があります。会社の担当部署か健康保険組合から申込書をもらい、提出することで申請が完了します。
申込書には会社や病院が記入する部分もあるので、早めの書類の取り寄せやママ自身が書き込めるところは書いておくなど、事前に準備をしておくと慌てずにすむでしょう。
(産前産後休業保険料免除制度の詳細については以下の記事も参考にしてみてください)
育児休業給付金
育児休業給付金とは、ママが育休中に申請すると支給される給付金です。支給の際は2ヶ月分をまとめて受け取ることになります。受け取れる期間は赤ちゃんが1歳になるまでですが、保育園に預けられなかったり配偶者が養育できなくなったなどの事情によっては、2歳まで延長できる場合があります。支給額は後述の「産休の給付金の計算方法は?」にて解説します。
申し込みの手続きは主に会社を通して行いますが、申請できるのは育休中だけです。受け取るために満たす必要のある条件や必要書類など、あらかじめ会社の担当部署に確認しておきましょう。注意したいのは、2ヶ月ごとに追加で申請をしなければならないという点です(※4)。次回申請書の提出が遅くなるとその分支給も遅くなるので、速やかに提出するようにしましょう。
(育児休業給付金については以下の記事も参考にしてみてください)
産休の給付金の計算方法は?

Recommended
おすすめ記事
授乳中のママへ贈る、カフェインレスコーヒー&ティーおすすめガイド
【確定申告・いつまでに?やるべきか?】わかりやすく順序だてて解説します!!
【夢占い】妊娠する夢の意味とは?何かの警告なのか?その対策とは?
【夢占い】妊娠する夢の意味と心理:状況、感情、登場人物から徹底解剖
妊娠中の性行為はNG?気になる疑問を徹底解説!
妊娠中に心と体を満たすプレゼント5選:本当に喜ばれるギフト選び
さまざまなサインがわかる!!妊娠中のおりものの目安について
【妊娠中のお腹の張りの不安について】原因と対策ーリラックスグッズ3選
【ほっこり】石原さとみ、日本アカデミー賞で“美しすぎるママ”姿を披露
【祝】辻希美さん5人目を妊娠!ママとしての強さと優しさに注目