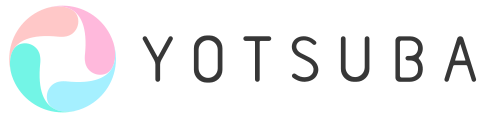帝王切開にかかる費用が高額!自己負担額と保険料は?出産費用を抑えるコツを紹介
帝王切開にかかる費用が高額であることをご存知ですか?この記事では帝王切開にかかる費用の平均や、その内訳などについて解説します。また、帝王切開で出産した場合に公的制度で受け取れるお金や、民間の医療保険の加入についてもご説明しますので、ぜひ見てみてくださいね。

帝王切開と自然分娩との費用の違いは、まず入院日数に差があることで生まれます。自然分娩の入院日数は産後5日間程度としている医療機関がほとんどです。それに対して帝王切開の場合、入院日数は産後およそ6~10日になります。また、帝王切開での出産後は個室となるケースも多いため、室料についても差が生まれやすいと言えるでしょう。
ただ、帝王切開と自然分娩には費用だけでなく、産後に受け取れるお金の額にも違いがあります。この後くわしく説明しますが、帝王切開による出産のほうが公的制度で受け取れるお金も多く、場合によっては民間の医療保険から給付金を受け取ることも可能です。
帝王切開の出産で公的制度で受け取れるお金は?

高額な費用がかかる帝王切開での出産ですが、正しく手続きをすれば公的制度によってお金を受け取ることもできます。そして、公的制度を活用すると、帝王切開による出産での自己負担額を大幅に減らすことも可能です。では、ここから帝王切開での出産において受け取れる公的制度のお金についてご説明します。
出産育児一時金
帝王切開での出産で受け取れる公的制度のお金には、出産育児一時金というものがあります。こちらは帝王切開に限らず、普通分娩の場合でも受け取ることが可能です。出産育児一時金は、本人もしくは夫が加入中の健康保険から支給されます。勤務先の健康保険や、自営業などの方は国民健康保険に申請をしておきましょう。(※2)
そして、出産育児一時金として受け取れる金額は42万円となっています。出産費用の多くをまかなうことができる金額なので、帝王切開にかかる費用を抑えるためには欠かせないお金だと言えるでしょう。出産する医療機関が直接支払制度に対応可能であれば、費用の総額から出産育児一時金を差し引いた金額を支払うだけですみます。
高額療養費
高額療養費も、帝王切開での出産で受け取れる公的制度のお金として挙げられます。こちらは月初めから月末までにかかった医療費が自己負担の限度額を超えた場合に、超過した分の金額が返ってくるというものです(※3)。帝王切開の費用も給付の対象内であり、本人もしくは夫が加入中の健康保険に申請すると受け取ることができます。
自己負担の限度額は、年齢や収入の金額などによって異なる仕組みです。収入が低ければ、自己負担の限度も低額となっています。また、事前に発行可能な「限度額適用認定証」を健康保険証と合わせて提示した場合、退院時に支払う金額は自己負担の限度額までです。
出産手当金

帝王切開での出産で受け取れる公的制度のお金には、産休を取ることで勤務先から給料が支払われないかわりに給付される出産手当金というものもあります。こちらも帝王切開に限らず、普通分娩でも受け取ることができるお金です。直近12ヶ月間の月収平均の3分の2が、産休の日数分給付されます。(※4)
正社員はもちろん、契約・派遣社員やパート、アルバイトであっても健康保険に加入していれば出産手当金を受け取ることが可能です。仕事をしていた妊婦さんは、忘れず加入中の健康保険に申請をしておいてくださいね。
(出産手当金については以下の記事も参考にしてみてください)
医療費控除の還付金
医療費控除の還付金も、帝王切開での出産で受け取れる公的制度のお金として挙げられます。医療費控除は、高額の医療費を支払った人が税金において優遇される制度のことです。こちらも帝王切開と普通分娩、どちらの出産においても対象になります。確定申告をして国税局や税務署に申請すれば、納め過ぎた分の税金が還付金として戻ってくる仕組みです。(※5)
医療費控除の対象となるのは本人・家族の1年間の医療費の合計が10万円以上、または所得が200万円未満であれば所得の5%以上の金額の場合となっています。還付される金額は、申告者の所得税率や申告する金額によって変わってくるでしょう。「確定申告のことがよくわからない」という方は、最寄りの税務署に直接足を運んで確定申告をおこなってみてくださいね。
(医療費控除については以下の記事も参考にしてみてください)
乳幼児医療費助成制度

乳幼児医療費助成制度も、出産後に受け取れる公的制度のお金として知っておきたいもののひとつです。この制度も、どういった分娩方法であっても申請が可能となっています。乳幼児医療費助成制度は、乳幼児の入院・通院における医療費の自己負担金を助成してくれる制度です。市区町村が主体となって実施しており、助成の範囲や対象年齢も地方ごとに異なります。
また、乳幼児医療費助成を受けるためには「乳幼児医療費受給資格証」を医療機関に持参しなければなりません。産後には速やかに役所で申請をおこない、受給資格証を発行してもらいましょう。産後すぐに赤ちゃんが入院してしまった場合にも、こちらの制度で入院費を抑えることができるケースもあります。
(産後の手続きについては以下の記事も参考にしてみてください)
Recommended
おすすめ記事
授乳中のカフェイン摂取は本当にダメ?影響と対策を徹底解説!
授乳中のママへ贈る、カフェインレスコーヒー&ティーおすすめガイド
【夢占い】妊娠する夢の意味とは?何かの警告なのか?その対策とは?
【夢占い】妊娠する夢の意味と心理:状況、感情、登場人物から徹底解剖
妊娠中の性行為はNG?気になる疑問を徹底解説!
妊娠中に心と体を満たすプレゼント5選:本当に喜ばれるギフト選び
さまざまなサインがわかる!!妊娠中のおりものの目安について
【妊娠中のお腹の張りの不安について】原因と対策ーリラックスグッズ3選
【ほっこり】石原さとみ、日本アカデミー賞で“美しすぎるママ”姿を披露
【祝】辻希美さん5人目を妊娠!ママとしての強さと優しさに注目