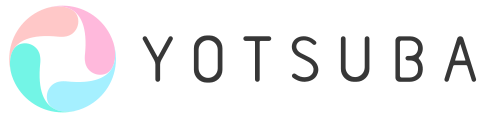育児休暇の男性取得率は?取得することでのデメリットがかなり多い?
政府が2024年までに男性の育児休暇率を13%にすると目標を掲げました。これは男性、女性ともに育児がしやすい社会を目指すための一環です。ところが男性の育児休暇取得率は目標に遠く及ばず。その背景には何があるのか、世界の動きと今後の可能性を探ってみましょう。
女性以上に男性は育児休業(休暇)明けの復帰が不安
育児をしながら仕事も続けたい、そう考える女性の多くが、育児休業(休暇)が終わった後、どのような働き方をするかについて不安を持っています。このときに正規労働から非正規労働(アルバイトやパート)に移行するという女性も少なくありません。
男性が育児休業(休暇)を取得する場合は、女性の不安どころではないでしょう。男性は一般的に、勤続年数が長くなるにつれ昇進・昇級していくというのが現状の日本の会社組織です。こうした社会の中で男性が育児休暇を取得するというのは少数派。復帰後に今までと同じポジションや地位が用意されているとは思えない、というのが本音でしょう。育児休暇を取るデメリットが大きすぎると感じるのも納得できてしまいます。

しかし、法律はちゃんと子育てをするための制度を用意しているのです。しかも、この制度を利用できるのは女性に限られたことではありません。たとえば「時短勤務」の制度です。この制度は「育児・介護休業法」という法律に定められたものですから、たとえ自分の務める会社で、だれも取得した前例がなくても申請できます。
ちなみに法律では「事業主は3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければならない」「短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置をする」と定められています。男性が育児休暇を取って、その後、時短労働制度を利用して子育てに関わることは、当たり前の権利だと言えるはずなのです。
育児に関して、男性側より女性側の固定概念も強い?

政府の調査によると、今の日本は、傾向としては男性も女性も仕事を中心に考えている社会です。ところが女性に対して「大黒柱となって働いてもいいですか」と質問すると「自分が稼ぎの中心になるのは嫌だ」と答える人が多く、この質問に対しては以前と変化はないようです。
また、ある雑誌の意識調査でも女性に対してどのような男性を求めますかとの質問に対して「育児や家事には積極的に分担して欲しいけれど、好きになる人は仕事をバリバリとやっている男性に惹かれる」という解答が多かったそうです。自己矛盾ですよね。男性も女性も共同して育児を楽しめる社会にするには、女性側の意識の変化も必要だと言えそうです。
つまり、法律での環境整備や支援が充実したり、企業内認識の改善が図られたりして、働く女性が出産することでのデメリットは少なくなりつつある一方、意識の変革がおいついていないのかもしれません。
子育て支援を進める訳

国立社会保障・人口問題研究所の発表によると日本の推計人口は、現在(2017年現在)の1億2675万人から2048年には9913万人へと減少し、1億人を割ると予想されています。出生率は減少傾向にある一方、高齢化はますます進んでいます。つまり、いままで現役世代と考えられていた世代の人たちだけでは日本社会は支えていけない時代へと突入してきているということです。
「男性」「女性」「老いも」「若きも」、1億総活躍を政府がめざす目的
そのため日本政府は年齢にこだわらず働きたい人が働ける環境を整備しています。育児・介護に関する法律の充実もそのひとつです。
女性が輝ける社会ってなに?政府の取り組みと女性公務員の現状

働く女性が増える中、政府も女性の活躍しやすい社会づくりを目指し、さまざまな法律整備を行っています。この対策は減少する労働人口を維持するためだけではなく、世界で女性が活躍している割合に日本も追いつくための施策でもあり、サービス産業が伸びている現状において、女性の視点や感性が必要とされている生産サイドからの要請も受けての対応だと考えられます。

女性の年齢別労働力率の推移を見ると、Mカーブと言われる減少が見られます。それは24歳から29歳で労働力率がピークとなり、一旦25歳から29.2歳あたりで凹み、30代後半にやや上昇するというカーブを描きます。つまり、24歳から29歳あたりに結婚・出産をするため労働力率が下がり、子育てが一段落した年齢で、やや復活していることを示しています。
ただ、子育て以後の職場への復活がピーク時の数字より低いことから、出産後は正規労働ではなく非正規での復帰あるいは離職を選ぶ女性が少なくないと言えます。こうした現状を回復するための施策として、政府では非正規労働の待遇改善や正規雇用の推進、長時間労働の抑制、フレックスタイム制など、働き方を見直す法律や制度を打ち出しています。
ちなみに女性公務員の場合を紹介すると、女性公務員は育児休暇として最大3年を取得することが認められています。また3年の育児休暇後の職場復帰については完全に実現されています。こうした制作は国家公務員の育児休業等に関する法律で、「育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない」と明記されており、復帰を望めば同じ条件での復帰が完璧に実現されるわけです。
世界の男性育児休暇取得率はどれくらい?
Recommended
おすすめ記事
4歳児向け知育玩具のおすすめ15選!発達を促して潜在能力を引き出すおもちゃを厳選!
お七夜の料理メニューは?手抜きでも豪華なお祝い膳の簡単レシピ!宅配についても!
水遊び用オムツのおすすめ11選!プールで使えて防水性ばっちりな商品を紹介!
生後4ヶ月の赤ちゃんの服装!サイズの目安や季節別の選び方・着せ方を解説!
子供の手洗い!習慣づけのコツや、正しい洗い方!楽しくなるアイテムも!
子供の中耳炎の症状は?自然治癒でOK?治療は必要?40度の高熱でお風呂はNG?
新生児から使えるチャイルドシートおすすめ20選!対象年齢など選び方のポイントも!
授乳中のカフェイン摂取は本当にダメ?影響と対策を徹底解説!
授乳中のママへ贈る、カフェインレスコーヒー&ティーおすすめガイド
【祝】辻希美さん5人目を妊娠!ママとしての強さと優しさに注目